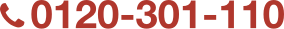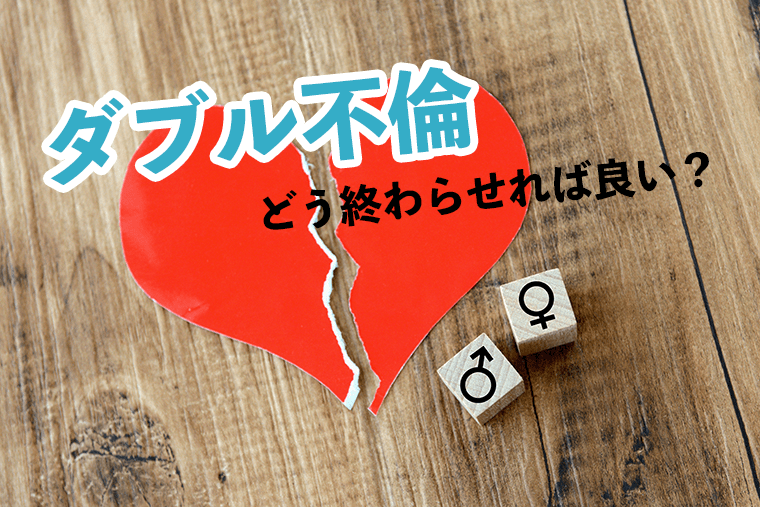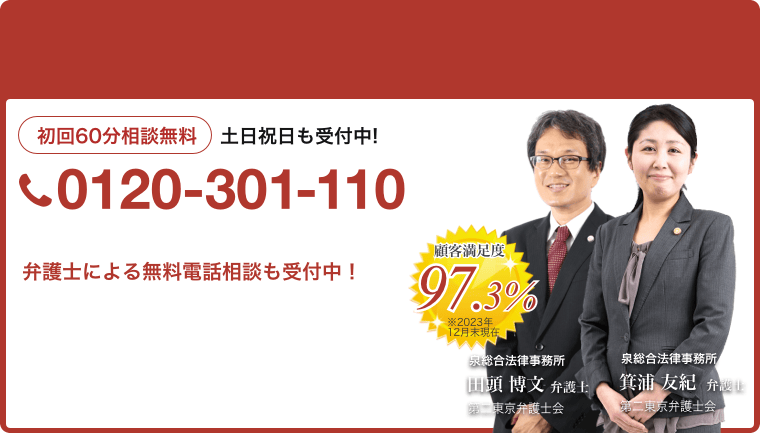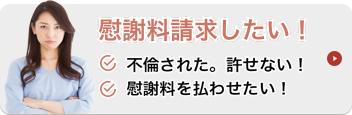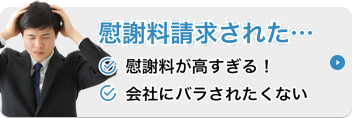旦那が社内で部下と不倫|浮気相手に会社を辞めさせる方法はある?
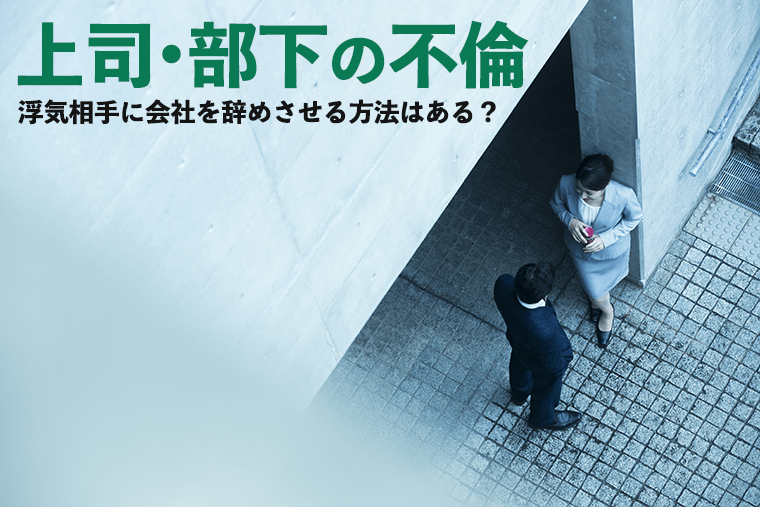
仕事上の上司と部下は、自然と共有する時間が長くなります。
「上司としての尊敬がいつの間にか恋愛感情に変わっていた」「部下として指導しているうちに魔が差した」ということはよくあるようです。
しかし、その上司や部下が既婚者だった場合、二人は「不倫関係」にあるということになります。
旦那や妻などの配偶者が社内で不倫をしていることを知った被害者の方は、不倫の当事者に慰謝料請求をすることができます。
しかし、被害者としては「たとえ慰謝料を受け取っていても、二人が同じ職場にいることに耐えられない」「不倫相手に会社を辞めさせたい・自主退職してほしい」と思うことでしょう。
今回は、特に「旦那が社内で部下と不倫をしている」という被害者の方に向け「旦那の浮気相手に会社を辞めさせる方法はあるのか?」という点を詳しく解説していきます。
目次
1.不倫行為と退職
(1) 部下を退職させる権利はない
配偶者とその部下の不倫関係を知ったら、誰もが憤りを感じると思います。
不倫は「不法行為」にあたり、不倫関係にある男女両方が被害者である配偶者に対して損害賠償責任を負います。
しかし、配偶者が出社する度に部下と会っていると思うと気が気ではなくなり、損害賠償請求では足らずに二人の職場を異なるものとさせたいと思うのは当然かもしれません。
不倫は確かに不法行為です。しかし、結論を言うと、不倫をしたからといって当事者に退職を強制することができる法的な権利はありません。
もちろん、部下の方が不倫について深く反省して、自ら「気持ちを新たに有責配偶者と関係がないところでスタートさせたいので自主退社します」と言ってきてくれる分には、敢えてこれを引き留める必要はないでしょう。
しかし、退職がこちらからの強要にならないようには注意が必要で、強要になってしまうと「強要罪」という犯罪になる可能性もあります。
なお、「有責配偶者である自分の配偶者に迫って転職させる」という方法は一案ですが、これは被害者である配偶者側の生活の基盤を脅かすことにもなるので、慎重な選択が必要です。
(2) 就業規則との関係
会社は自社の社内規定として、民法上の責任とは別に、不倫などの不法行為については懲戒の対象としていることもあります。
不倫は業務には関係ないプライベートなものとはいえ、社内に不法行為をしているカップルがいるということはコンプライアンス上望ましくないですし、会社の風紀が乱れる可能性があるので、会社にバレた場合は何らかのお咎めがある可能性があります。
懲戒のレベルは会社にもよりますが、異動・減給・降格、最悪の場合は解雇ということもありえます。
特に上司の方に対しては、部下を指導する管理職という立場を重く見られ、会社での評判にも少なからず傷がつくと思われます。
上司である有責配偶者が、昇給・査定など、人事上で部下に対して持っている権利を悪用して部下に不倫関係を強要した場合、部下は「故意過失によって被害者である配偶者に損害を与えた立場」ではない(=そもそも不法行為者ではない)ということになり、慰謝料支払義務を負わないこともあります。
一方、言い逃れのために、実際は自らの意思で不倫関係に入ったのに「上司から強要された」と嘘をつく部下がいないとは限りません。
実際に強要の事実がないならば、部下が自分の意思で不倫関係になったということがわかる証拠(不倫関係で積極的な態度をとっているLINEやメール等)を保存し、備えておくことが必要です。
2.不倫相手への対応策
では、相手方を辞めさせることができない以上、不倫相手である部下にはどのような対応もとることができないのでしょうか。
(1) 不倫関係を清算する
まず、不倫慰謝料でご自身が受けた精神的ダメージについてきちんと金銭的な賠償を受けることが必要です。
不倫慰謝料は、不倫の相手方(今回のケースでは部下)だけでなく、不倫をした配偶者(上司)にも請求することができます。
婚姻している男女は、互いに相手以外の異性と性的な関係をもってはならないという貞操義務を負うことになります。
それに違反して不倫をしたほうの配偶者は「有責配偶者」といい、自分の配偶者が不倫によって負った精神的損害について賠償責任を負うのです。
ですが、有責配偶者と今後も結婚関係を継続し、夫婦仲を修復していくことを目指すのであれば、不倫の相手方にのみ不倫慰謝料請求を行い、不倫関係を清算させることになるでしょう。

[参考記事]
浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求したい!
(2) 今後の私的な接触を避ける誓約をする
不倫関係を清算する場合、示談書(誓約書・合意書・和解書)を作成することが通常です。
口頭だけでの約束ですと支払いが行われない可能性がありますし、後から「言った・言わない」「払った・払わない」の水掛け論になる可能性もあります。
不倫の示談書(誓約書)には、不倫慰謝料の金額や支払い方法だけでなく、以下のような「今後一切の連絡を絶つ」という誓約をとる文言を入れ、抑止力を持たせるために違反した場合の違約金を定めることが多いです。
【記載例】
「乙は、甲に対し、今後丙との交際をやめ、合理的理由なく丙に連絡しないことを約束する。約束に違反したときは、乙は、違約金として1回あたり金○○万円を甲に対し支払うものとする。」
ですが、上司・部下の場合は、職場が同じです。片方が辞めない限り「接触しない」ということは難しいでしょう。
そこで、社内不倫の場合では、「業務以外での私的な接触を避ける」という誓約をとることが現実的な対応策と言えます。
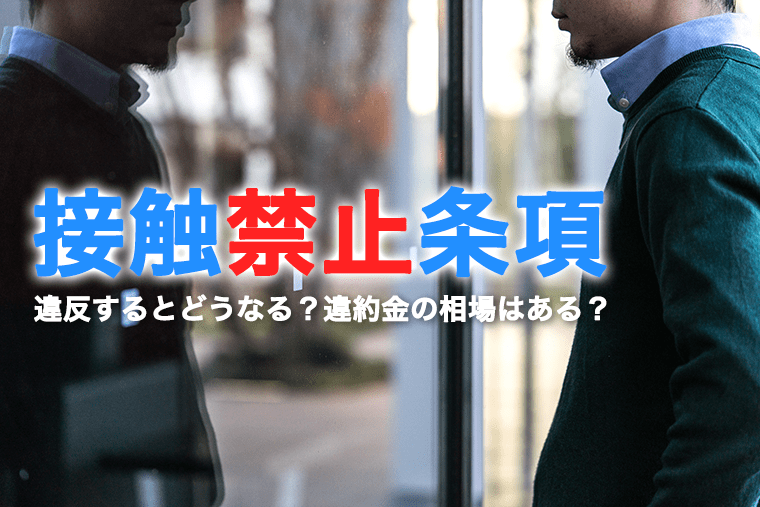
[参考記事]
接触禁止条項に違反するとどうなる?違約金の相場はある?
なお、示談書(誓約書)で今の仕事を辞めることを求める内容を記載することはできません(書いたとしても、職業選択の自由を制限する内容に強制力はなく、これに違反したからといって違約金を支払ってもらえる可能性はないでしょう)。
(3) 職場の人事部等に相談する
私的な接触を断つといっても、上司・部下の関係でいられると、どこまでが業務上でどこまでが私的な接触なのかが難しく、不安に思う場合もあるかも知れません。
誓約書をとってもやはり信用ができない、不安が残るという場合には、最終手段として職場の人事部・総務部などに事情を相談し、穏便に異動や配置転換をしてもらないか相談してみるという手もあります。
しかしながら、これは諸刃の剣ともいえます。
先述の通り、有責配偶者が不倫をしていたという事実が会社に知られると、会社からの評価が下がり、減給・降格などのリスクが発生するのです。
人事部や総務部は秘密裏に処理をしてくれるはずですが、急な人事異動などはどうしても職場で噂となる可能性はありますし、不倫の噂が立つと、有責配偶者が事実上職場に居づらくなってしまうという場合もあります。
なるべく職場の力を借りず、有責配偶者や不倫相手とのやり取りで完結することを目指すべきでしょう。
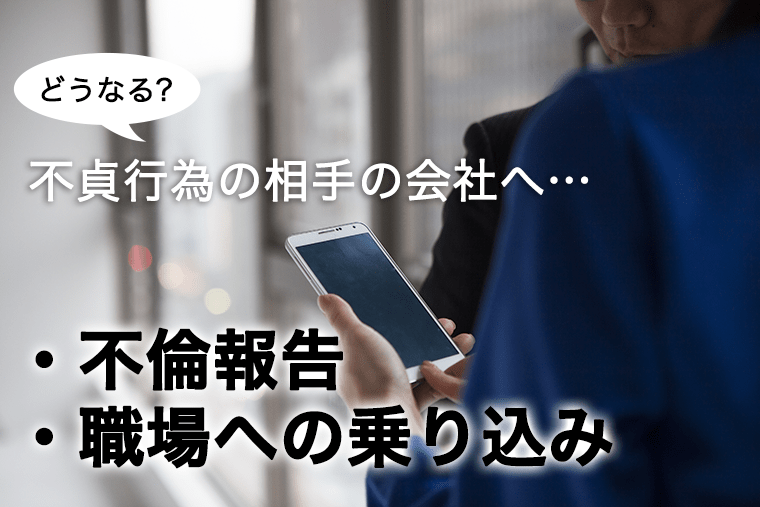
[参考記事]
不貞行為の相手の会社へ不倫報告・職場に乗り込むとどうなる?
(4) 不倫の事実を言いふらすのはNG
いくら不倫相手に不満があったとしても、不倫相手の職場に不倫の事実をみだりに言いふらしたり、嫌がらせをしたり、ネットに書き込んだりしてはいけません。
こういった行為をうかつにしてしまうと、相手のプライバシーの侵害や名誉毀損になってしまうこともあります。
名誉毀損になると、刑事罰と対象ともなってしまいます。程度にもよりますが、相手からプライバシー侵害や名誉毀損で民事上の請求を受けたり、警察に相談されて捜査対象になってしまったりすることもあります。
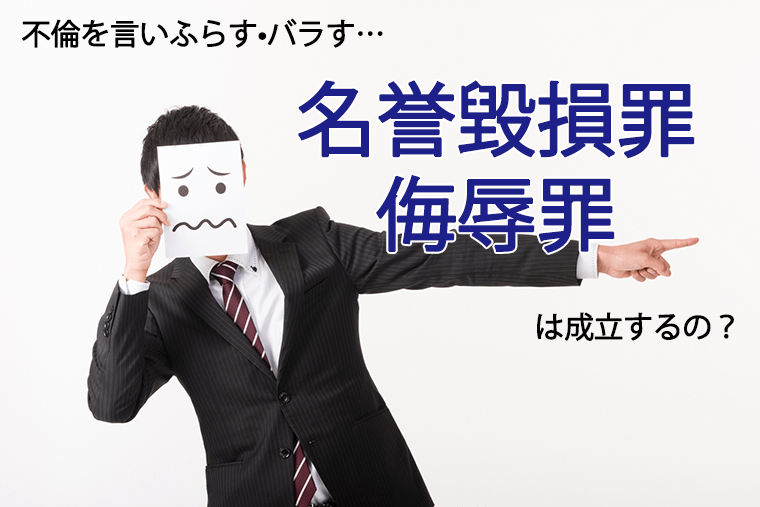
[参考記事]
不倫を言いふらす・バラしたら名誉毀損罪や侮辱罪は成立するか
3.不倫問題の解決は弁護士に相談を
配偶者と部下の不倫はとてもショックですが、感情的になって退職を迫ったりはせず、冷静に対処することが必要です。
不倫の証拠をおさえたら、早くから弁護士に相談することがお勧めです。
不倫問題は、当事者間が直接やり取りすると感情が混じって話しがこじれることも多いです。不倫関係に実績がある法律事務所に示談交渉をお願いする方が、スムーズに解決できるでしょう。
不倫問題の解決・不倫慰謝料の請求を検討されている方は、一度泉総合法律事務所へご相談ください。